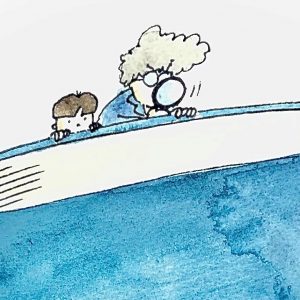こどもの哲学を忘れるな。
「こどもの哲学を忘れるな」
僕の心にすっと入って、居続けるこの言葉。
不思議とネットで検索してもヒットしない。誰の言葉なのか、どこで耳にしたのか、誰に宛てたものなのか、何も分からない。
まるで神話の作者が不明なように、その起源が明かされることはない。それは神託にも似た、簡潔な命令文。
直感的に、「これはとても大切なことに違いない」と思った。
僕はこの言葉を、「人はなぜ生きるか。死んだらどうなるか。宇宙に果てはあるのかなど、素朴で根源的な問いを心のどこかに持ち続けること」と理解している。
それは、いつのまにか忘れてしまった、こどもの哲学だ。
不思議がいっぱいのこどもと
物分かりのよい大人。
こどもといると、繰り返し浴びせられる言葉がある。
「なんで?」
「どうして?」
大人にとってはあたり前のことも、こどもの眼には不思議に映る。
「なんで虫歯になるの?」
「どうして電球は光るの?」
「どうして春になると桜が咲くの?」
思うに、ものごとの原因や理由を考えるのは、人間に備わったごく自然な心性の一つだ。そういえば、僕も小さい頃、たくさん質問しては親を困らせていたような。───なんだか遠い昔に感じる。
いつからか僕は質問をしなくなった。
答えが分かったわけでもないのに。
誰かに質問したり、自分で調べることをやめただけじゃなく、問うことそれ自体をしなくなった。
それはつまり、「不思議に思うこと」をやめてしまったということ。
分からないままに、不思議と思う感性だけが、次第に麻痺していく。いつしか「そういうものだ」と受け入れていた。
歯を磨かなければ虫歯になるし、スイッチを押せば電球は光るし、春には桜が咲く。そこに不思議はない。我ながら大人だ。物分かりのいい、大人。
でもそれは、ある意味当然だと思う。
現実では考えることより、こなすことが優先される場面は多い。「なんで?」「どうして?」ばかりでは日常が止まってしまう。生きることはノンストップだ。「考えてる暇はない。とにかく、目の前のタスクをこなさないと」
僕たちはきっとどこかで、「物が分かっていない」ということに、折り合いをつけたのだ。チコちゃんに、「ボーッと生きてんじゃねーよ!」と言わても仕方がない。
だけど、こう言い返してもいいだろう。
我々はボーッとどころか、必死に生きている。
不思議を理解したいという、
抑え難い願い。
けれども人は、そう簡単に問うことをやめない。やめられない。
社会に問いが封じられ、抑圧されても、心の奥底には不思議と思う感性や、知りたいという根源的とも言える欲求が眠っているはずだ。それは何かの拍子に再び動き出す。
それどころか、生涯にわたり問いを持ち続け、その探求に情熱を注いだ大人も少なくはない。
私が研究を行うのは、自然の不思議を理解したいという抑え難い願いから。
最も美しいものとは神秘です。
これを知らず、もはや不思議に思ったり、驚きを感じたりできなくなった人は死んだも同然です。
アインシュタインの言葉だ。
世紀の天才は物分かりがいいのではなく、その分からなさに、不思議さに、驚嘆した。その神秘を「美しい」と感じた。彼にとって、それを理解したいというのは、「抑え難い願い」だった。「なんで?」「どうして?」を大人になっても言い続けた。
彼は、こどもの哲学を決して忘れることがなかったのだ。
それにしても、「死んだも同然」とはなかなか強烈だ。さすがに言い返したくもなる、「大人にだって事情がある」。ただ、それだけ、悔しいけど、うなずける部分が多いのも事実。
現に、「なんで?」「どうして?」と尋ねるこどもの表情は魅力的だ。愛情の反対は無関心、とはよく言うが、彼・彼女は、「世界への関心」に満ちている。
そして、その関心や問いによって、こどもの日常がとまることはない。それどころか、日々更新されていく。
むしろ、人は問うことをやめたときに、停滞が始まるのかもしれない。
「問いの密度」が
答えを充実させる
僕は天理教を信仰している。
宗教は哲学ではない。神から答えが与えられる。そして、それを素直に受け入れることが信仰的な徳目とされる。そういう世界に僕は生きている。
だが、“それだけで” いいのだろうか。
こどもから向けられる純粋な「なんで?」に大人のほうがハッとさせられる。そんな経験が思い当たるのは、僕だけではないはずだ。
きっと、彼・彼女らはまだ生きることに “慣れて” いない。まだ手垢のついていない、初学者なのだ。
私たち大人が、いくら用意された答えを切り貼りしても、こどもの哲学にフタをするだけではないか。
もし、我々が神の言葉に “慣れて” しまったら、それは「もはや不思議に思ったり、驚きを感じたりできなくなった」のであり、その信仰は「死んだも同然」なのではないか。
そうではない在り方があるはずだ。
天理教の中山正善二代真柱は、天理教の聖典『おふでさき』に向かう姿勢について、こう述べている。
おふでさきというものは、通り一遍に鵜呑みに出来るような対象ではなくて、それを熟読し、或は懐疑しつつ、その本意を探り進む事によって、更に信仰を深めて行く指針となるものである事を諸君に知ってもらいたい。
この言葉は、『おふでさき概説』の「序説」に出てくる。それも、最初の頁に。
懐疑は否定を意味しない。
それは、大切に思うがゆえの、真摯な姿勢から生じる。
私たちは問うことをやめてはいけない。
それは、こどもの持つ素直さ。
切実な問いこそが、新しい世界を拓く。
問いの密度が答えを充実させる。
───それは、「求道」ではないか。
「諸君に知ってもらいたい」、二代真柱は自身の希望で、そのセンテンスを結んでいる。
僕はそこに、「こどもの哲学を忘れるな」と同じ響きを感じている。

文:可児義孝 絵:たづこ
tabinegoto#23